人員構成の多様化、約6割の企業で進む/メイテック調査
エンジニア派遣のメイテックは2日、製造業の人事担当者らを対象とした
「ダイバーシティ・マネジメントに関する調査」の結果を発表した。
3年前と比較した人員構成を尋ねたところ、約6割が「多様化している」
と回答。特に活用度が高まっている人材は「外部人材」が41.6%、
「外国人」 が29.2%、「女性」が16.9%などとなっている。
http://www.meitec.co.jp/news/pdf/2008/081002.pdf
外国人介護士、約4分の1の施設で雇用/人材派遣会社調査
福祉の人材派遣を手がけるニッソーネットはこのほど、首都圏の介護老人
施設等を対象に実施した「外国人介護士に関するアンケート調査結果」を
発表した。それによると、約4分の1の施設が「在日外国人介護士を雇用
している(したことがある)」と回答。「真面目さ」と「明るさ」を評価する一方
で、「記録業務での支障」や「職員とのコミュニケーション」 などを問題点
にあげている。
http://www.nissonet.co.jp/pdf/news_080924.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
外資系で勤務していると比較的当たり前の単語ですが、日系企業だとあんまりメジャではないようですね、ダンバシティ。
まぁ、メイテックの調査でも、「女性」の増加を「多様化」とするあたり、まだまだ文化の多様化までは道のり遠いかも、という感じですね。まぁ、それは段階的にしか進まないので。
でもまだまだ外国人は移民問題もかねあって、なかなか難しいのでしょうねぇ。
外資だとそのへんにアングロサクソンやインド人が歩いていたりするし、そもそも上司がそんな人たちだったりもするので、否が応にも意識せざる得ない。
その一方で、もうひとつの記事にあるように「在日外国人介護士」の記事にあるように我々の生活にゆっくりとではあれど、文化の多様性はしみこみつつある。
でもニッソーネットの調査記事を見る限りでは、サービスの現場にも比較的スムーズに入り込めているようですね。それはちょっと安心。もっと悲惨な評価を懸念していたので。
そしてやはり最大の難関である「コミュニケーション」は課題になるんだなぁ、と。
このコミュニケーションが、バーバルなものかノンバーバルなものか気になる。
日本人だと、ついついバーバルさえ何とかなれば、と思いがちだけど、けっこうそうでもないのだわね。
とくにサービス事業においては、ノンバーバルでのダイバシティがかなりの重点を占める。
その辺まで踏み込むと、まぁ、学術調査のレベルに入り込んじゃうのかも(笑)
2008年10月10日金曜日
ダイバシティってご存知ですか?
2008年10月9日木曜日
製品導入時の情報収集に関する調査ご協力のお願い
なんというか、面白そうなので、ご紹介。
まだ自分では対応できていませんが。。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『製品・サービス導入時の情報収集活動に関する調査』ご協力のお願い
〜ご回答いただいた方から抽選で20名様にギフトカードをプレゼント〜
https://aida.nikkeibp.co.jp/Q/R005009VK.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日頃は「日経ものづくりNews」をご利用いただき、ありがとうございます。
現在、「日経ものづくり」では『製品・サービス導入時の情報収集活動に関する
調査』を実施しております。
この調査は、業務上で製品やサービスを購入・導入される際の情報収集活動や、
各ものづくり関連企業のホームページを実際にご覧いただいた印象などをお尋ね
するものです。
調査結果は、集計の上、各企業が読者の皆様とのコミュニケーションを考える際
の参考資料として活用いたします。
ご多忙の折り勝手なお願いで誠に恐縮ですが、趣旨をご理解の上、ご協力を
賜りますようお願い申しあげます。
日経BP社 日経ものづくり
■調査名
『製品・サービス導入時の情報収集活動に関する調査』
■ご回答URL
https://aida.nikkeibp.co.jp/Q/R005009VK.html
※ご回答は、本メールをお受け取りになった方のみ、お一人一回でお願いいた
します。
■謝礼
ご回答いただいた方の中から抽選で以下のものをプレゼントいたします。
・全国共通ギフトカード 5000円分……… 20名様
■ご回答締切
2008年10月19日(日)23:59
■本調査に関するお問い合わせ
※下記URLから「お問い合わせフォーム」へ入り、
調査番号:R005009VK
調査名 :製品・サービス導入時の情報収集活動に関する調査
をご記入の上、送信してください。
⇒お問い合わせフォームのURL
( https://bpcgi.nikkeibp.co.jp/research/rp-form.html )
※本アンケートは日経BP社の委託により、日経BPコンサルティングが
実施しています。
【ご回答内容と個人情報の取り扱いについて】
●日経BP社と日経BPコンサルティングの個人情報保護方針、およびアンケート
回答者規約に従い、責任を持って管理いたします。
●あらかじめこれらをお読みいただき、ご了承の上、ご回答ください。
《日経BP社の個人情報保護方針》
http://corporate.nikkeibp.co.jp/information/privacy/
《日経BPコンサルティングの個人情報保護方針》
http://consult.nikkeibp.co.jp/consult/privacy.html
《アンケート回答者規約》
http://consult.nikkeibp.co.jp/consult/aida/mn_kiyaku.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎日経BPコンサルティングは、日経BP社全額出資の「調査・コンサルティング
会社」です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎日経BPコンサルティングは、個人情報保護方針と情報セキュリティ規定順守を
含む機密保持契約を日経BP社との間で結んでおります。
=====================================
2008年10月8日水曜日
立正大学〈ケアロジー〉公開講座 無料ご招待!
ケアロジーという単語には、なんとなく好きになれない響きが。。
「癒し」同様のそこはかとない違和感を感じてしまうのですわ。
なんだろう、倫理学とは何が違うのだ?
宗教学までは踏み込んでないだろうし。。
しかし立正大ってことは、やや宗教なのか?
それとも宗教の換骨奪胎を目指しているのか。。
そのあたりは興味深い。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆「立正大学〈ケアロジー〉スペシャルカレッジ」開講!◆◆
http://www.ris.ac.jp/event/contents_info.php?contents_id=472
----------------------------------------------------------------------------
〜現代の諸問題をケアする学問「ケアロジー」とは?〜
280名様を特別無料受講ご招待
スペシャルカレッジを、無料で聴講するチャンスです!
■■■■■■■ 「立正大学〈ケアロジー〉スペシャルカレッジ」■■■■■■■
◇「人間のケア」を総合テーマに、スペシャリストの生の声で学ぶ、感じる ◇
http://www.ris.ac.jp/event/contents_info.php?contents_id=472
立正大学では、現代の諸問題をケアする学問「ケアロジー」を追及するとともに、
モラルと専門性をかけあわせた人材『「モラリスト×エキスパート」を育む。』
を教育目標として掲げています。
「ケアロジー」は人間の諸問題をケアするための学問です。多くの方にその本質を
ご理解いただけるよう、公開講座を開催いたします。
当公開講座では、各界のスペシャリストである下記3名の方を講師として招聘いた
しました。
○第1回講師: 篠田正浩 氏(映画監督)
「瀬戸内少年野球団」「札幌オリンピック」「スパイゾルゲ」他、
数々の代表作で知られる。
○第2回講師: 岸朝子 氏(食生活ジャーナリスト)
主婦の友社で「栄養と料理」の編集長を務め、その後料理栄養に関する雑誌
や書籍を企画編集。TV「料理の達人」では人気審査委員として出演。
○第3回講師: 立花龍司 氏(コンディショニング・ディレクター)
高校・大学の野球選手生活の後、学んだ指導学でコンディショニングコーチ
として、日本球界、NYメッツでコーチ経験を積む。
2007年度からは、千葉ロッテマリーンズのコンディショニング・ディレクター
に就任。
(コンディショニング・ディレクター=チームの体力的要素に関する統括部門
の管理職)
つきましては、当公開講座に280名様を無料招待いたします。
(応募者多数の場合は抽選。当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます)
◎--------- 立正大学〈ケアロジー〉スペシャルカレッジ 開講概要 ---------◎
■第1回: 11/12(水)18:30〜20:00【講師:篠田正浩 氏】
■第2回: 11/19(水)18:30〜20:00【講師:岸朝子 氏】
■第3回: 11/26(水)18:30〜20:00【講師:立花龍司 氏】
■会場: 立正大学 大崎キャンパス(東京都品川区大崎4-2-16)
■参加費用: 無料
■申込締切: 10/31(金)17時必着
■申込方法:「はがき」「FAX」「E-mail」にて。
下記必要事項を必ずご記入のうえ、下記申込先にお送りください。
・受講希望日
・講師名(1枚につき1講義)
・氏名(ふりがな)
・年齢
・郵便番号
・住所
・電話番号
■申込/問合わせ先:
立正大学スペシャルカレッジ運営事務局(栄美通信内)
〒104-8189 東京都中央区銀座1-15-6 KN銀座ビル
TEL: 03-3561-8506
FAX: 03-3561-5347
E-mail: rissho-s@eibi.co.jp
※受講者には11月3日発送(予定)で受講券を送付いたします。
ホームページはこちら>>
http://www.ris.ac.jp/event/contents_info.php?contents_id=472
■主催: 立正大学
■後援: ダイヤモンド社
2008年10月7日火曜日
企業発ベンチャー
「企業発ベンチャー」、大手10社の取組みを調査/日本経団連
日本経団連はこのほど、報告書「企業発ベンチャーの更なる創出に向けて」
を発表した。企業の有する技術・アイデア等の資源を活用し新規事業を創設
する「企業発ベンチャー」推進の取組みについて、松下電器、富士通、JTBなど
会員企業10社へのヒアリング調査の結果をまとめたもの。
報告書は、公募制度の広報、社員に対する基礎的能力教育や、ベンチャー
設立後のマネジメント人材の確保などを課題にあげている。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/journal/times/2008/1002/07.html
====================================================
マネジメント人材はどこでも不足してますね。。
企業発ベンチャーのひとつの目的はマネジメント人材を育てることでなかったかしらん?
そもそも大企業において子会社する効果だったはずなのだけど。試行として。
ベンチャーって銘を打ってしまうと(うーん、「姪を売ってしまう」と変換しやがった。。鬼畜な感じ)そういう位置づけではなくていずれはきりはなれて自立してくれることを期待するのかしらん。でも総合商社なんて、定常業務がベンチャーみたいなもんだからねぇ、こういう悩みは無いのだね。
でも新卒で入社して、おんなじようなスキルセットだったはずなのに、なんでこうなるんでしょう?
そういうところが企業文化なんだろうけど、不思議ですわ。
2008年10月6日月曜日
教員というサービスプロバイダと給与
●日本の教員の労働時間、OECD平均を大きく上回る
経済協力開発機構(OECD)はこのほど、「図表で見る教育2008年版」を発表した。
男性の大学進学者数が女性を上回る国は、OECD加盟国の中で日本、ドイツ、韓国
とトルコの4カ国。日本の高等教育機関への進学率は男性が52%、女性が38%で
その差が最も大きい。また、初等・中等教育の教員の法定労働時間は年1,952時間で、
比較可能な17カ国のうち最も多く、OECDの平均(1,651〜1,662時間)を大きく上回っている。http://www.oecdtokyo.org/theme/edu/2008/20080909eag.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●一律支給の見直しを提言/教員の残業代、実態に応じ
教員の残業代に相当する「教職調整額」の在り方を議論していた文部科学省の
有識者会議は8日、本給の4%を一律で支給している現行制度を見直し、
勤務実態に応じた「時間外勤務手当」の導入を検討するよう提言した。
(共同通信)
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/gyousei/20080917b.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●教員の平均年齢、40歳代半ばに上昇/文科省・学校教員統計調査
文部科学省はこのほど、2007年度「学校教員統計調査(中間報告)」の結果を発表した。
教員の数は、小学校が約39万人で前回調査(04年)と比べ0.3%の増加。
中学校が約23万2,000人(1.1%減)、高等学校が約23万4,000人(3.6%減)となっている。
教員の平均年齢は小学校が44.4歳、中学校が43.8歳、高等学校が45.1歳で、
いずれも上昇傾向にある。
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/002/2008/index.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
うーーーーーーーーーーーーん。これはひどい。
ちなみに個人的な事情を明かしておくと、親戚一同かなりの「先生一家」なので、教員については近親憎悪か(笑)かなり厳しい目線を持っている。公務員だからプロ意識が無いとか、更新がないから緊張感が無いとか、競争がないから改善が無いとか、愛情とかに話を持ち込むから思想的に歪んでいるとか、けっこう否定的に捕らえてました。
ちなみに上記につらつら書いたことについては、某元大臣ではないが、暴言といわれても撤回する気はありません。まぁ、いろいろ改善されつつあるようですが。まぁ、ここで日教組の問題を語る気はない。
それ以前にサービス業として成立する土壌が無いことをはじめて知りました。
浅学とは恥ずかしいことですね。残業代もなく、個人の想いだけで休日もなく働いてたんですね。
これは良くない。対価の交換が無いサービスなど、Frontlinerの暴走を止める手段が無い。
さらにいうのであれば、これは大変申し訳ないが、サービスの品質は一般論として低下する(かなり気を使ってみた)。プロフェッショナルサービスということなんだろうか?しかしそうだとしても、業務遂行に時間的/物理的な拘束を要求するのであるから、やっぱりその分の対価は支払うべきなのである。
あるいは成果給でも持ち込んで、ただし競争とサービス品質の改善を促進するべきである。そして評価システムを導入する。これがなければ、サービスレベルは設定されず、それはサービスシステムとして顧客のインボルブメントを適正化できない。つまり、仕組みとしてモンスターペアレントは生まれるべく設計されてしまっているのである。
聖職者が金の話をしてはいけないのかもしれないが、聖職者とて人の子である。
そして後戻りできなくなった世代が中心のプロバイダになっていることが如実に現れている。
現象としてみる限り、まったくプロフェッショナルサービスのプロバイダではない。
公務員がプロフェッショナルサービスを提供する、という矛盾が根本にある。
2008年10月5日日曜日
階層化している中学受験向けサービス
「中学受験専門の家庭教師ドクター」だそうです。
おいらが個人的に何がすごいと思ったか、というと、あくまで、塾の補完機構として家庭教師を配置している点である。つまり、家庭教師or塾という対立構造におくのではなく、あくまで塾を「正」として、その補完に効果を限定している。大げさに言うとネットワーク外部性をレバレッジしているかんじかしらん。
なので、「中学受験専門のプロ講師集団(SAPIX・日能研・四谷大塚の講師)が運営」という売り文句が成立する。
最初に見たときには非常に違和感があった。なぜなら、塾のSubstantialとして家庭教師を考える、という思い込みがあったため、上記の売り文句は組織への裏切り行為となるのでどうして成立するんだろうかしらんと思ったまでであるが、世の中、そんなに甘い次元ではなく、すでに両方を同時に採用するという選択肢が登場するんですね。。認識を新たにしました。
単層のレベルではなく階層化したサービスを両方購買する必要があるんだなぁっと。いやはや、いまや常識なのかもしれないけど驚きました。
でも、塾の特性に応じて成績を伸ばすための手法を提示しているところ、あと、Frontlinerである家庭教師とBackSupportの「プロが直接相談にのってくれる」というシステムは、非常に安心感を生みますね。
サービスとしてはプロフェッショナルタイプのサービスなので、Frontlinerのパフォーマンス依存になるところをうまくカバーしたシステムだと思う。
比較的情報提供も豊富で好感が持てるんじゃないでしょうか?
しかもこのビジネスモデルがすばらしいところは、リソース(講師陣)のリスクが比較的少ないところである。本業の塾と、ビジネス的にもリソース的にも依存可能であるため、本業へのオプションとしてこのビジネスに参画できる。ここはすばらしい。
サービスコンセプトはかなり好感が持てますが、そんなに費用をかけられる層がどれくらいあるのかがサービスビジネスとしては興味深いところですな。
2008年10月4日土曜日
Good!コンブネーションダンスキャンペーンご紹介
CM等で見かけるものですが、なかなか面白いと思っていたところ、キャンペーンでダンス動画を募集をしているようです。みなさまご応募なさってはいかが?
優秀な作品はサイト上で発表!またフジッコ製品の詰め合わせのプレゼントもあるそうです。
募集要項はこんな感じ。
~~~☆☆☆~~~☆☆☆~~~☆☆☆~~~☆☆☆~~~
ワンフレーズだけでの応募もOK!だから赤ちゃんでも応募可能☆
CMで使用している「ふじっ子煮」のパッケージを持つ必要はありません。
~~~☆☆☆~~~☆☆☆~~~☆☆☆~~~☆☆☆~~~
なるほどふじっ子煮のパッケージは要らないそうです(笑)
ちなみに踊りはこんな感じ。
関西版ってのがあるんだ、へぇ。
ワンフレーズだけでもOKだから赤ちゃんでもOKってのはどうだろう?
赤ちゃんてのはどこまで赤ちゃんなんだ??
親が後ろから躍らせても良いのかなぁ。
それだと面白くないなぁ。
おたくのお子様とか、勝手に踊っているんじゃありませんか?
であれば、ちょっとビデオをまわして撮ってみるだけで応募可能ですわね。
ついでに正確な踊りを教えてみましょう
芸能人への道も開けるかも?
ちなみにわが家では、このCM以来、サラダにふじっ子を混ぜるという献立が一つ増えました(笑)
2008年10月3日金曜日
外国人労働者受入れ
外国人労働者の新しい受入れシステムを提言/日本経済調査協議会
日本経済調査協議会は16日、報告書「外国人労働者受入れ政策の課題と
方向」を発表した。外国人労働者を「高度人材」と「特定技能人材」に分け、
それぞれの受入れシステムを構築すべきと主張。「高度人材」は積極的に
受け入れ、定住化を認める。「特定技能人材」については、働きながら
能力・キャリアを開発できる仕組みをつくり、1〜5年の滞在期間でスキル
アップすれば「高度人材」に転換することも可能とする。
http://www.nikkeicho.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
移民の1割が中国出身/OECD「移民アウトルック」
経済協力開発機構(OECD)はこのほど、2008年版「移民アウトルック」を
公表した。06年の移民を出身国別にみると、中国が全体の11%を占め
トップ。次いで、ポーランドとルーマニアの東欧2カ国が続いている。一方、
移民の受入れが多かったのは米国、韓国、スペインなど。前年と比べ、
移民受入れの増加率が高かった国はポルトガル、スウェーデン、
アイルランドなどで、減少率が目立ったのオーストリアとドイツだった。
また、08年版では移民の雇用状況に焦点を当て、受入国の労働市場への
統合に関する「得点表」を初めて提示。移民と受入国労働者との賃金格差
について分析している。
http://www.oecdtokyo.org/theme/mig/2008/20080910sopemi.html
http://www.oecd.org/dataoecd/30/42/41275636.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
うーん、微妙ですね。。
生まれた国が違うだけで、こう格差があるっていうのはどうなんでしょう?
そこはかとなく漂う選民思想。
国益というボーダー概念が非常にいやらしく感じてしまう。
仕方ないことだとは思えど、そういうものかと。
そんなことに違和感を覚えられるのは、「持つ者の優越感」か?
別段憐れみの感情があるわけではないが、なぜ移民が規制されるのか?
移民などしなくともできる仕事が多くなっているだけに、規制の意義がわからない気もする。
対面が重要な仕事=サービス業はポテンシャルがあるが、それだけに文化粘着性を帯びるので、よりいっそう移民には向いていない気がするし。
でも、この特定技能とかそうじゃないってのは国内でも職業差別にならんかね?と思わないでもない。職業に貴賎無し、というのはまやかしだったってことかしら。
選民思想と職業の差別、微妙な問題に向き合うことになるんですね。
個人的にはすべてのボーダーを取っ払っちゃえば良いと思うけど、そのときに自分が何かを失うときっと騒ぎ立てることになるんでしょうねぇ。。
中国の人口が世界の20%を占めるなかで10%なので、相対的にはそれほど多くは無い。
それに対してインドの移民が非常に少ないってことがわかる。
このへんは文化とビジネスモデルの違いですかね。
2008年10月2日木曜日
靴に個人や個性は宿るか?
この感覚はわからないなぁ。
比較的理解可能なところとしては、お気に入りの靴下か?
それも無いよなぁ、きっと。
靴下は使い捨てのイメージが強いからなぁ。
そこまで、靴に思い入れがあるのだろうかね?
アメリカでは靴はずぅっと履いているものだからね。
こだわりが出るのは判らなくも無いので、そういう感じになるのかもしれない。
かつて(かなり、かつて、だけど)日本人は電車に乗るのに下駄を脱いでしまう国民性なのでやっぱり理解できないわね。すっごくどうでもよい話だけど、鉄道開通時の忘れ物は下駄とか靴の類だったそうなので。(うーん、ほんとにかなりの、かつて、だ)
こんなところからも異文化交流って難しいと思う。たいしたことではないけど、なんかが違うって思うのはこういうところなんだろうなぁ。どうしたってその人の「育ちの違い」は出てしまうのだよね。
さて、死刑囚になったとき、執行されるときに要求するものは何ですか?
なかなか難しい。やっぱりタバコすわせて欲しい、くらいかなぁ。
なんだかちょっとさびしいね、と考えさせられたので(笑)
2008年10月1日水曜日
10/12「今から備える!不動産活用セミナー」参加者募集!
うーん、前々から企画してたんだろうけど、時期的には最悪ではないかね??
もしかすると、逆境の中に活路があるのかもしれないけど、サブプライム問題の渦中に不動産活用もどうなんでしょう?まぁ、土地がある人はいいのかもしれないなぁ。
でも不動産の証券化とか、そもそもその概念が間違っているといわんばかりの空気の中でどうなんだろう?
所詮は美人コンテストでしかないあぶく銭なので、余っている人は活用できるけど、そうでない場合は今取るべき選択でないと思いますが、ちょっと「ハッピーリッチ」は「イタイ」気がしますね。。
++——————————————————————————————————++
一歩前に踏み出しませんか?
土地活用の悩みを解決。不動産でハッピーリッチになる。
++——————————————————————————————————++
参加費無料!事前登録制 残席わずか!!
++——————————————————————————————————++
ご参加の方にもれなく、山崎隆氏の新刊書籍
『お金に困らないマイホームの買い方・つかい方』をプレゼント!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇◆ 今から備える!不動産活用セミナー
◇◆ 10月12日(日)13:00〜 / 渋谷エクセルホテル東急
◆ お申込み・詳細は
http://www.business-talent.com/tokyu-homes/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〜 一歩踏み出すために、こんな悩みにお答えします。〜
相続する土地を有効活用したいけど、なかなか踏み出せない。賃貸物件
を建てたいが、管理はどうすればいい?税金はどうなるの?将来の年金
不安に備えて賃貸経営をしたいけど、良い相談相手がいないなど、土地
オーナーの悩みは多岐にわたります。
そんな悩みに【今から備える!不動産活用セミナー】がお答えします。
日本テレビの人気番組だった「おもいっきりテレビ」でおなじみの
松原英多氏、不動産のカリスマコンサルタントの山崎隆氏が講演。
また、土地オーナーの悩みに丁寧にお答えする個別相談会も同時開催いた
します。賃貸経営・不動産の建て替え売却・リフォーム・節税対策・相続
対策・立ち退きなどの悩みに専門家がお答えいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ 今から備える!不動産活用セミナー
主催:株式会社東急ホームズ
協力:ダイヤモンド社広告局
10月12日(日)13:00開場 13:30開演
渋谷エクセルホテル東急 6Fプラネッツルーム
————————————————————————————————————
◆ 第1部
| 「欲があるから脳は成長する、欲張りは美徳」
| 松原英多 医学博士
| 「おもいっきりテレビ」でおなじみの松原英多氏が、
| 脳を活性化する欲張りと土地活用の効用を語ります。
◆ 第2部
| 「不動産でハッピー・リッチになる」
| 山崎 隆
| 財営コンサルティング代表取締役、CFP
| 不動産のカリスマコンサルタントが、豊かな老後を導く
| 土地活用の成功の方法と決め手を解説します。
◆ 同時開催 個別相談会
| 土地オーナーの悩みに専門家が丁寧にお答えします。
▽ プログラム詳細・お申込みは、Webをご覧ください。 ▽
http://www.business-talent.com/toukyu-homes/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
————————————————————————————————————
【お申込みに関するお問合せ】
今から備える!不動産活用セミナー事務局
TEL:03-3431-7046(平日:10:00〜18:00)
————————————————————————————————————
2008年9月30日火曜日
「うつ」多様化時代の対策セミナーのご紹介
個人的にはWeb配信でこの値段は無いんじゃないの?しかも自分のところで出版する本の宣伝セミナーなんでしょう?と思ってしまいますが。。まぁ、興味深い話題なので。
「『うつ』多様化時代」という表現がすばらしい!
うつが多様でなかった時代があるかのようで(笑)
本質的にうつなんぞ解明できていないでしょうに。
「風邪ひいた」と同じであろう、要するになんだか精神的に調子外れた状態をさす。
何がストレスになるかわからないし、同じ原因やシチュエーションでなる人もいればならない人もいる。
なんだかわからないから、うつ、なんである。
風邪だっておんなじ。風邪ってどういう状態?
のどが痛いとか鼻が詰まるとか、症状多様だけど、医学的な定義は無い。
まぁ、定義があるだけ、うつのほうがましか??
でも定義ったって、かなりあいまいですけど。
なんだか気分が落ち込んだらうつなんである。(大うつ、からが病気扱いなので、たしか)
そんなこと、ふつーに生きていたら起きるだろー、ってことが「うつ」なんです、はい。
健康とは何か、って話と同じで、定義はかなり困難なはず。
プラクティカルには、医者が認めれば病気になるはず。
さぁ、暇な人は、自分の調子が良い状態と普段との差分をリストして記憶して医者にそれを症状としてお医者様にお話してみましょう。うつ病には簡単に認定してもらえます。演技力というか信憑性にかなり依存するけど(笑)
だから根が深い問題なのだ。どこかが病気かわからない。
でも明らかに病気な状態はわかる。それはけっこう悲惨な状態にならないとわからない。
なぜなら、境界事例が決められない、という大問題をはらむためである。
まぁ、いまゆる健康診断とおなじで「まだ大丈夫」と思わずに、「危ないかな」とおもったら専門家の意見を聞くしかないんだろうなと思いながら、日常的に、この状態はうつの初期症状、と知りながら、「まだ大丈夫」って思っちゃうのだわね。難しい、やっぱり。
そういう意味で興味深いのだ。
----------------------------------------------------------------------------
◆「うつ」多様化時代の対策セミナー◆
今求められる「実践的」ストレスマネジメント教育
〜仕事を減らさず、うつ病を減らすには〜
【10月16日(木)開催/参加申込み受付中】
----------------------------------------------------------------------------
●人事ご担当者必見!
今、職場では「うつ」が多様化しています。社員の心の病の増大は企業に
とっても大きな損失であり、メンタルヘルス不全の予防・対策は、ここ数年、
企業が取り組むべき課題として大きく取り上げられるようになりました。
しかし、そのような状況にありながら、適切な対策を講じている企業は
どれほどあるのでしょうか。
本セミナーでは、管理職への教育を第一と捉え、管理職が部下のストレス状況
を理解するうえで必要な心構えと知識、ならびに部下のストレス耐性を高める
コミュニケーションの手法を、ダイヤモンド社が今秋発行予定の『管理職向け
ストレスマネジメントブック』の著者である筑波大学教授・松崎一葉氏が、
まったく新たな切り口で解説します。
また、本セミナーはインターネット上で動画配信されますので、
当日ご来場できない方も受講いただくことができます。
詳しくは下記をご覧ください。
【開催概要】
■日 時:2008年10月16日(木)14:30〜16:30終了(14:10より受付)
■会 場:ダイヤモンド社 石山記念ホール(渋谷区渋谷1-1-8)
http://www.dia-ishiyama-hall.jp/hall/accessmap.htm
■対 象:企業の人事・人材開発・教育・研修のご担当者様
※研修、コンサルティングをビジネスとされている方、
個人の方からのお申込みはお断りさせていただいております
■受講料:5,250円(税込)/1名様あたり ※Webセミナー配信も同額です。
■定 員:50名
■詳細・お申込みはこちら>>
http://jinzai.diamond.ne.jp/seminar/utsu_seminar.shtml
2008年9月29日月曜日
チャンス発見コンソーシアム 11/1 博士講演会
「まれだが意思決定にとって重要な事象・状況である「チャンス(リスク)」をいかにして気付き、理解し、行動していくかを追求し」ているチャンス発見学、なのである。ひらめきとかも包含しているようです。でもやっぱり、胡散臭い響きを感じてしまうのはおいらだけ??
●データ結晶化の研究も含めて、きたる11・1に、
●未来を「知る」ためには、未来を「作る」姿勢が大切です。
11・1には、システムデザインを行う際の要求獲得技法についても
博士論文が登場します。
●以下にプログラム概要を掲載します。
詳細情報の更新はチャンス発見コンソーシアム
http://www.chancediscovery.com/の「イベント案内」をご覧下さい。
日時: 11・1(土) 午後1:00〜午後6:30
場所: 東京大学工学部8号館内
スケジュール:
午後1:00〜午後3:00 修士学生 (数名)
演題・イノベーションゲーム・会話分析など
午後3:00〜午後3:55
前野義晴氏 (博士(システムズ・マネジメント))
「ゼロ頻度事象を可視化する:テロからアートまで (仮題)」
午後4:00〜午後4:55 久代紀之氏 (博士(工学))
「進化型要求獲得の技法: 製品デザインと今後の展開 (仮題)」
午後5:00〜 討論会
「博士 vs アホ: いずれがイノベーションを生むのか?」
※ 決して冗談ではなく、真剣な議論です。
午後6:30〜 懇親会
2008年9月28日日曜日
ガートナージャパン Symposium/ITxpo 2008のご紹介
世の中の「IT」という領域がどれぐらい行き詰っているかわかる内容になっています。そういう意味ではかなり価値のあるシンポジウムです。いわゆるInnovativeなものはありません。
というとかなり怒られるかもしれないが、でも残念ながら、本質的なイノベーションは見当たらない。現在あるものを変えていくレベルに過ぎない。完全にビジネスに取り込まれてコモディティ化していく流れが明白な内容になっている。感動的に「新しい」ものは見当たらない。
工場がオートメーション化していくのと何も変わらない、そこなるのは、ほとんど生産工学の世界で語られていることを、ITという世界で焼きなおしている発想がほとんど、としか思えない。
なぜ、こんなにInnovativeでなくなったのか?
所詮は技術が確信していく流れを概念が追従していただけで、概念が先行することは無いことを立証しているに過ぎないのかしら??
技術が行きついて、人間の想像力を超えてしまうと、超えてしまっているだけに人間ではイノベーションに生かすことはできない、というジレンマなのかなぁ。
これ以上便利になってどうする?ということ??便利さが突き抜けると不便になる、というジレンマも同根である。選択肢が増えて自由が大きくなって、どんどん便利になるはずなのに不便に感じる。
こんなに便利になったがゆえに、不都合が多くなる。
このへんがITという概念の限界なのかもしれませんね。
しょせん技術主導の概念だったので。
まぁ、先端を見ているとそう感じるだけで、実際に世の役に立つまではもうしばらく時間がかかるし。
そのあいだに、Googleの次、を見出すことはできるのかなぁ。。
++——————————————————————————————————++
日本開催13回、世界7ヶ所で開催する最大級かつ最も信頼を得ているITイベント
今年も10月27日(月)からの3日間、東京・お台場で開催いたします。
++——————————————————————————————————++
9月30日(火)まで、お得な割引価格にてお申込みいただける早期割引キャンペー
ン実施中です。ぜひ、この機会に参加をご検討ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇◆ Gartner Symposium/ITxpo 2008
◇◆ --- IT in the Business & The Business of IT ---
◆ 10月27日(月)・28日(火)・29日(水) / 東京・台場
http://www.gartner.co.jp/symposium/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〜 新たな時代、新たなビジネス、新たなIT 〜
今、日本企業に求められているものは、ビジネスを持続させるとともに、新た
なグローバル価値の創造と、徹底した効率性を両立することです。また、企業の
社会的責任が問われて久しい中、真にサービス指向を実践し、人や社会に優しい
企業を目指していくことにも注力する必要があります。
そのためには、これまでのやり方や考え方だけではなく、新たなITによる新た
なビジネスを追求することが求められます。例えば、「ビジネスもITを前提とし
て設計する」といったような考え方を強めていくことも重要です。
ガートナー リサーチの今年1年間の集大成として、国内外からの豊富な事例に
基づく実践的なアドバイスをお届けするGartner Symposium/ITxpo 2008。
ITにかかわるすべての意思決定者にとって、新たな方向性を見出すきっかけと
なれば幸いです。
Symposium/ITxpo 2008 チェア
ガートナー リサーチ
バイス プレジデント 兼 最上級アナリスト
亦賀 忠明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ IT最適化のためのSymposium/ITxpo活用方法
————————————————————————————————————
あなたが現在抱える一番の課題、悩みは何ですか?
Symposium/ITxpoは、問題解決と意識改革をもたらす、
ガートナーのすべてを結集した3日間です。
▽ 活用方法の詳細はこちらから ▽
http://www.e-gartner.jp/symposium2008/symposium/process.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ Symposium/ITxpo 2008 テーマトラック
————————————————————————————————————
これまでに皆様よりいただいたご意見や最新の市場動向から、今年は、
以下12のテーマに沿って、60以上の専門セッションをご用意しました。
◆ IT in the Business
| ビジネス課題に応えるIT
| ITリーダーと語る
◆ Business of IT
| 新時代のCIOの役割
| ITガバナンス
| 情報活用
| アプリケーションとアーキテクチャ
| セキュリティとリスク管理
| ITインフラストラクチャとオペレーション
| ソーシングとベンダー管理
| 戦略的テクノロジ
◆ Market Trends
| テクノロジ市場の競争と機会
| ITデマンド調査に見るユーザーの実態
▽ プログラムの詳細につきましては、Webをご覧ください。 ▽
http://www.gartner.co.jp/symposium/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ 開催概要
————————————————————————————————————
【会 期】 10月27日(月)・28日(火)・29日(水) / 3日間
【会 場】 ホテル グランパシフィック LE DAIBA(東京・台場)
【主 催】 ガートナー ジャパン株式会社
【後 援】 社団法人 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)
特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 ほかを予定
【参加対象】
・CEO/CIOをはじめ、経営のためのITを追求している経営者層
・企業においてIT環境を提供する立場の、IT部門の責任者
・日常の事業活動においてITの活用を迫られる経営/事業企画部門の責任者
など、企業レベルのIT投資・導入に関わる全ての意思決定者
-----------------------------------
【ITコーディネータの方 必見!】
◆ ITコーディネータ知識ポイントを取得 ◆
ITコーディネータの方は、知識ポイントを取得できます。(最大16時間)
————————————————————————————————————
【登録に関するお問合せ】
Gartner Symposium/ITxpo 2008 登録事務局
TEL :03-3496-1039 FAX :03-3496-1057
Email :gartner@event-information.jp
————————————————————————————————————
2008年9月27日土曜日
背が高い人々、幸福感もより「高い」?
背が高い人々、幸福感もより「高い」=米調査
2008年 09月 12日 17:28 JST
[ニューヨーク 11日 ロイター]
背が高い人々は概して、背が低い人々よりも高い幸福感を感じていることが米国で行われた調査で明らかになった。「ギャラップ─ヘルスウェイズ幸福指数」を調査したデータによると、背の高い人たちの方が人生への満足感が高く、より前向きの感情を持っている傾向があった。研究チームは声明で「自分の人生に対して最低の評価を行った男性は平均すると、男性平均身長より4分の3インチ(1.9センチ)余り身長が低かった」としている。また、同チームの計算によると、身長が1インチ高くなる毎に、世帯所得が4%アップするのと同程度、人生の満足感が高まるという。
© Copyright Thomson Reuters 2008. All rights reserved.
ほほう。調査データって一人歩きするという現象の一つですね。
経年でデータ取ってみないと証明はできませんね。
でもさらに細かくデータを取得して、1cmあたりで「幸福指数」(これがまたすごい名前ですが。。)がいくつ上がるのかのトレンドなんかを出してくれると爆笑物です。
身長が1cm伸びるあたりであなたはこれだけ幸せになれるんです、なんて、シークレットブーツの宣伝文句としては抜群ですよねぇ。そもそも幸福指数を信じることができれば、ですけどね。
「身長が1インチ高くなる毎に、世帯所得が4%アップするのと同程度」の幸せが得られるそうです。
世帯収入も同じ場合「背が高い方が稼ぎ方が4%へたくそ」ということになるわけですね。
いやはや馬鹿馬鹿しい、ともいえないのかなぁ。
経年のデータを取って欲しいなぁ、やっぱり。
幸福指数の構成要素も知りたいなぁ。
収入以外で客観的なデータは何が入っているのかなぁ。
けっきょく表現できなくて現金換算しているところを見るとやっぱり無理なんじゃないのかなぁ。
世帯収入というのがまた微妙で、本人の稼ぎが悪くても、背が高い方が稼ぐ配偶者を得やすい、ということになるのかもしれない。
ぜひ体重でもやってもらいたい。こっちは比較的可変だから無理なんだろうなぁ。
でも不変なものをネタにしてこの手を話題を出すというのは、比較的危険なことだと思うんだけど、どう落とし前つけるんですかね?子育てにあたって、背が伸びる努力をしたほうがよいぞ、ってことか?
身体的な価値観って比較的流動的なものなので、なんともこのレポートの結果自体を評価しづらい。
でもなんだか、面白い。
2008年9月26日金曜日
早稲田大学グローバルイノベーションフォーラム2008のご紹介
うーん、いろんな意味で微妙。ここには書けませんが。
まぁ、でも聞いておいて非常に有益そうな講演だと思う。
内田先生がものづくりの座長というのも意外ですが。
ただし、こんな日中にほんとうにいけるかどうかはかなりのリスク(爆)
これを無料というのも太っ腹な大学である。
人脈のなせる業か?それは恐ろしいものである。。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇◆ 早稲田大学グローバルイノベーションフォーラム2008 ◆◇◆
【日 時】 2008年10月8日(水) 9:40〜17:00(9:20開場)
【会 場】 早稲田大学 大隈講堂
【主 催】 早稲田大学、早稲田大学ビジネススクール(WBS)
【共 催】 日経ビジネス、日経ベンチャー
【後 援】 中小企業基盤整備機構、日本ニュービジネス協議会連合会、
日本経済新聞社、テレビ東京(予定)
【協 賛】 コメリ、新日本有限責任監査法人、ミロク情報サービス
【定 員】 400名 ※定員になり次第、申込を締切らせていただきます。
【受講料】 無料(事前に本Webサイトで受講申込をお願いします)
事前登録制・受講申込や詳細はこちら=http://ac.nikkeibp.co.jp/nb/waseda/
日本企業の置かれた現状や将来像を、作家・堺屋太一氏と
早稲田大学大学院・内田和成教授が、また、「グローバル化」と「イノベーション」
という時代の求めるキーワードに、どのように取り組み、実行し、成功させようと
しているかを、ものづくり企業、サービス企業、そしてベンチャー企業のトップが
それぞれ語ります。
また、早稲田大学の教授陣、『日経ビジネス』『日経ベンチャー』のデスク・編集長ら
によるディスカッションも交えながら、日本企業が活力を取り戻すためのヒント
を探ります。
詳細・お申し込みはこちら=http://ac.nikkeibp.co.jp/nb/waseda/
2008年9月25日木曜日
"樹を植えること"を贈り物に。
先日のおでかけツアー以来、なんだか「いいひと」モードなので感激気味。
うーん、われながら浮かれているなぁ。
実際はそれどころじゃないんだけど(笑)
長い努力になりますよね、植林活動。
CSRをななめに見ると「売名行為」にしか見えないしかないのだけど、それにしたって、そこに一定の投資をしていることは評価してよいんじゃないでしょうかね?いまひとつSRIが日本で流行っていない気がするのはおいらだけかしら。もう少しこういうところも企業価値評価に参入するべきではと思う。
で、グローリーフである。
ロゴはこんな感じ。まぁ、そのまんまですね。

コンセプトとかロゴだけ見ていたらNPOなのかと思ったら、ITXの関係会社がやっているようです。オリンパスの関連会社ですね。なるほど、オリンパスなら自然が残らないと困る企業だしね。撮るものが魅力的で無くなったら映像業界は死活問題だし。けっこう、環境問題は間接的にインパクトがあるに違いない。
そういう意向なのかどうかはわからないけど。
こういう事業を取りまとめるというのは、それにしたって儲からないのだろうから、この事業自体はNPO的なんでしょうね。すばらしい。会社の社会貢献を比較的「当たり前」と思ってしまう日本人に価値観においてこういう活動を続けるのは本当に難しいのだと思う。頭が下がります。
でも、1社だと続けられなくても、こんなふうに協賛の形であれば続けやすそう。いいアイデアだともいます。
そしてこういった活動につきもののキャラクターですが、命名の機会があったみたいですね。
でも終わっちゃっている。。ちょっと残念?
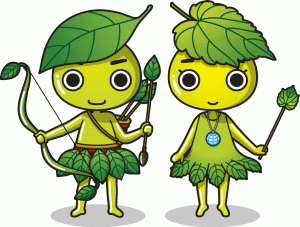
そろそろ名前を公表して欲しいものでありますな。
http://a8buzz.a8.net/tb/s00000007830003/a06061896469/001
2008年9月24日水曜日
「テレワーク試行・体験プロジェクト」参加企業を募集
総務省と厚生労働省は2008年度「テレワーク試行・体験プロジェクト」への参加企業を
10月22日まで募集する。同プロジェクトは「テレワーク人 口倍増アクションプラン」の一環
として昨年度新設され、今年度は参加企 業・団体を200社に拡大して実施しているもの。
体験プログラム参加に必要なシステムは国が無料で提供する。http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/telework/index.htm#table25
(テレワーク人口倍増アクションプラン)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/others/telework.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
すばらしい。ぜひ進めて欲しいですね。
環境保護の観点からも、人間が移動しない方が位置エネルギーの変動がないからよっぽどよい。何で会社で働かなきゃいけないのか、この意義を問い直すいいチャンス。ただし、行き過ぎると、それこそ、何で会社に所属して働かなきゃいけないかわからなくなるに違いない。全員がフリーランスで契約する会社で何がいけないのか?労働契約の中途半端さが如実になるリスクはあるけど、でも相当な期間我々は会社に所属して働くことに慣れさせられちゃっているので、急速な変化は無いと思うけど。
物理的に会社に行く意味ってなんでしょう?
これはけっこう、いいテーマだと思う。
セキュリティだ、勤務管理だと、管理面からのビューでは会社に来てもらうに越したこと無いが、それが最も生産性が高く、効果的なスタイルなんであろうか?
ブルーカラー層はある意味やむをえない。なぜなら、機材等を考えると投資は集中的に行われることから、生産設備等に物理的に近接することが要求されることが多いためである。
その、一方でホワイトカラーは、場所に縛られる必要性は無い。
顔を見て仕事をしたい、とか、すぐ話ができる距離にいてくれないと困るなど、やや情緒的に偏るポイントを排除してしまえば、一定以上、会社に物理従属してはたらく必要は無い。
ただし、会社への帰属意識の低下が生産性に与える影響は決して小さくないはず。
このリスクやセキュリティ管理の重要性を正常に理解して展開することが肝要となるでしょうね。
あと、接点業務が最も重要となるサービス業の大半については適用できない。
そのときに管理畑の人間がテレワークを採用していると、不公平感を生む出すし。
募集中といわれているが、意外とはハードルは高いのかも
2008年9月23日火曜日
裁判員に選任されたときの休暇取得
労務行政研究所が11日発表した「裁判員制度実施に向けた企業の対応調査」
の結果によると、社員が裁判員に選任され休務する場合の取扱いを
「すでに決めている」企業は46.5%だった。その対応は
「従来から定めている公務に就く場合のルールを適用」が62.8%で最多。
「裁判員休暇を新設」した企業は23.9%だった。
休務時に休暇を付与する場合の取扱いについては、「有給扱い」が9割
を占めている。
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/9684
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
約6割が「裁判員休暇制度」を導入/日本経団連アンケート
日本経団連は17日、一部会員企業に対して実施した「裁判員休暇制度に
関するアンケート集計結果」を発表した。それによると、社員が裁判員に
選ばれた際の特別休暇制度について「導入済み」または「導入を決定済み」
の企業は63%。残りの37%も「導入を検討」している。同休暇を「有給」
とする企業は全体の86%、「無給」が2%、「未定」が12%だった。http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/064.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まぁ、妥当な結果だと思うけど、残りの10%は厳しい会社ですね。
国会議員に立候補するなど、本人が好き好んでいく場合には無給というのはわかるけど、行かないと罰則適用されるという裁判員制度の場合まで、会社のために働くわけではないから無給というのは、やや理不尽。
それに意外と、皆さんルール好きなんだなぁと。
「公務」を会社に任せるのが不安なんでしょうかね。
「裁判員休暇を新設」という企業が25%近い、つまり4社に1社くらいというのは、驚きの数字である。
ルールなんて、大きく決めておきに限るのにね。そうしないと運用の例外が拾いきれない。こんな風に例外的なイベントが発生するたびに、いちいち就業規則を改定するのか?なるほど、社会保険労務士が不当所得を得ているとしか思えないわねぇ。いらないでしょう、いちいち。
そのたびに係争のリスクをあげるよりは、管理者と従業員の関係をルールではなく信頼ベースに戻さないと、どう決めたってもめることになる。立法の理念というものが無い規則はたいていにして係争の種にしかならないもの。
なんてことを考えてしまうのだけど、たしかに公務に関しては国会議員に就任した場合も含まれちゃうので、そのリスクを回避するのであれば、個別に定めたい気持ちはわかるが、やはり法的厳密性よりも運用的バッファを残した規則のほうがスムーズでしょうねぇ。改定が多い規則なんて、個人的には信じたくないし。
2008年9月22日月曜日
ガソリン代を安くする知恵
そんなときにふと見たチラシ。我が家に行きつけはエネオスだが、エネオスカードに入るとお得、という紹介がされていた。年会費も無料だし、かなりお値打ちな感じ(笑)
んで、調べてみるとやっぱりこーゆーサイトは世の中には存在するのね。というご紹介。
ガソリンカードランキング
なるほどガソリン代 節約術というのはカードに限らずいろいろあるのだね。
けっこう、こういうことを一生懸命やれる人って、ある意味尊敬する。
ガソリン節約ブログ、ガソリンカード クチコミなど、勉強になりやす。頭が下がります。
ついつい個人的にはこういうことにけちけちするよりもルーズに楽したいタイプなので。。。
でもこういうことを日頃から関心を持つべきなんでしょうねぇ。満タンにしないでコツコツ通うとか、そうなんだけど、確かに説明は正しいんだけど、うーんん、むずかしい。
少なくとも、ガソリンが値上がりになるからといって、わざわざ遠くの安いガソリンスタンドに出かけていって、その日の5円とか10円のために、何時間も並ぶという効率の悪さに比べると、精神衛生上良いのではないかと思う。
それに、冒頭に書いたリーマンではないけれども、あれこれ株やらFXやらでこせこせ小遣いを稼ぐことに比べると、よっぽど健康的に感じる。
倹約という言葉の魅力ですね。エネルギーの無駄遣いにならないことが重点かなぁ
そんなことするくらいなら車に乗るなといってしまっちゃあ、話にならない。
2008年9月21日日曜日
SIer向け!高収益実現の具体策を伝授するセミナー
船井総研ってこんなことまで手を伸ばしていたのかと。
SIerに絞って経営を語る講演って確かに珍しいかも。
これはこれとてなかなか興味深い。
ただ、中堅・中小のSIerさんって、どこまで単独で案件運営しているのかしらん。
どこかのSIerとかベンダの動きを見続けるほうが重要に思うのはベンダにいるせいかしら。
製品を持っていて、それを展開する会社をSIerと呼ぶならそれは定義が違うと思うし、ややおいらにはセグメントがわかりにくいセミナーだなぁって感じですわ。
うーん、大企業にいるやつにはわかんねーんだよ、と言われてしまうとそれまでか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【書籍「IT一番戦略の実践と理論」出版記念】
『SIerのためのビジネスモデル再構築・実践セミナー』
http://coin.nikkeibp.co.jp/coin/wat/semi/0809/
◆ ◆
マーケットを数値で徹底分析し、
売れる商品・仕組みを創る「IT予算帯方程式」の全貌
<<自社・顧客・市場・商品を数値で論理的に分析する手法を伝授!>>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎時流適応で基礎力を身に付けよ!◎
◎一番マーケット選択の公式「船井流IT予算帯方程式」とは?◎
◎自社の強みを発見する分析法とは?◎
◎勘違い営業をなくすマーケティング、セールス戦略とは?◎
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【講師:船井総合研究所 経営コンサルタント 長島淳治氏】
<<2008年9月30日(火)青山ダイヤモンドホール(東京・表参道)>>
◎残席僅か!お早めにお申し込みください!◎
http://coin.nikkeibp.co.jp/coin/wat/semi/0809/
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
【開催にあたって】
米国のサブプライムローン問題と世界的な原料高は、企業のIT投資を確実に減ら
し始めました。2005年度、2006年度、2007年度と好業績をおう歌してきたSlerへ
の風向きが変わり、経営の先行きに対する危機感が急速に高まってきています。
こうした現状を生き抜くために、SIerには何が必要なのでしょうか。本セミナー
の講師である船井総合研究所の経営コンサルタント・長島淳治氏は、この難問に
対する答えを示しています。すなわち「時流適応 力相応一番」の勧めです。
それは、他社に負けない一番になれる市場を見つけ、その分野に全力を注ぐこと
で強い企業になろうというものです。
長島氏の考えが興味深く有用だろうと思われるのは、一番を実現させる独自の手
法まで存在することです。長島氏が考案した「IT予算帯方程式」というものを使
って、自らが実現可能な範囲で一番になれる市場を定量的に見つけることができ
るのです。その上で、見つけた市場に向けて売れる商品を作っていくことで、企
業の収益力を高めることができます。
また長島氏は、技術者出身の社長が多い中堅・中小のSIerにはマーケティングと
セールスについて正しく理解し、適切に取り組むことが大切だとも指摘していま
す。
本セミナーでは、ユーザー企業のIT投資に割く予算額から自社の経営戦略を練る
この「IT予算帯方程式」の考え方から、効率的に顧客を集める戦術までを、4時間
に渡り徹底的に解説します。
2008年3月に95%の受講者の皆様から圧倒的な支持を集めたセミナーの内容を大幅
加筆・修正して書籍化した「IT一番戦略の実践と理論」の出版記念講演会です。
ITサービス会社の経営・管理層、営業部門、商品開発部門の方、必聴です。
是非、この機会にご参加ください。
◆全受講者中95%から圧倒的な支持を集めた◆
◆ セミナー書籍化の記念講演会を開催! ◆
◎「自社のマーケティングや営業活動が間違いだらけであることに気づいた」
◎「数値化と論理的なマーケティングのイメージが理解できた」
◎「いままで弊社が何のビジョンもなく、いかにやみくもにやっていたかが
浮き彫りになった」
◎「IT投資の市場規模、算出方法がとても参考になった」
◎「具体的な話が多く、期待以上の収穫があった」・・・・・・・
◎残席僅か!お早めにお申し込みください!◎
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ http://coin.nikkeibp.co.jp/coin/wat/semi/0809/
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■ 開催概要 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ■日 時:2008年9月30日(火)13時00分〜17時00分(開場:12時30分)予定
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ■会 場: 青山ダイヤモンドホール(東京・表参道)
┃ http://www.diamondhall.co.jp/access/index.html
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ■主 催:日経ソリューションビジネス
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ■受講料:書籍「IT一番戦略の実践と理論」(長島淳治・著、9月23日発行)付
┃ ※書籍は当日受付にてお渡しいたします。
┃
┃ ▼セミナー単独申込コース: 23,000円(税込み)
┃ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ▼日経ソリューションビジネス購読付きコース:33,000円(税込み)
┃ セミナー受講料に加えて10,000円で、日経ソリューションビジネスを
┃ 6ヶ月(12冊)お読みいただけるコースです。
┃ ※「日経ソリューションビジネス」ご購読者 現在のご購読期間に12冊
┃ 購読延長付き
┃ ※一般の方 「日経ソリューションビジネス」最新号から12冊購読付き
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■ プログラム ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【講師プロフィール】:
船井総合研究所 戦略プロジェクト本部チームリーダー
経営コンサルタント 長島 淳治 氏
大手SIerでの営業を経て、2004年に船井総合研究所に入社。以来、中堅・中小
のITサービス会社を専門にコンサルティング活動を行う。「経営者を元気にす
る」をモットーに経営計画作り、マーケティング、組織活性化を支援。日経ソ
リューションビジネス誌において「中堅・中小SIer必読!ビジネスモデルの再
構築法」、ITproにて「成長の壁を突破するソフトハウス経営塾」を執筆。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ セッション1 13:00〜14:30
『自社の強みや顧客の状況を数値で徹底分析する「IT予算帯方程式」
まずマーケットを「知る」ことから攻略が始まる』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中堅・中小のITサービス会社がビジネスモデルを再構築するためには、まず自社や
顧客のことを客観的に知らなければなりません。そのためには自社を数字で徹底的
に分析したり、顧客を定量的、定性的に理解しなければなりません。そうすること
で、その先に正しい戦略が見えてきます。このセッションでは感覚から脱却し、数
字の経営を実践するにはどうすべきかを解説します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ セッション2 14:45〜16:00
『市場分析から「誰に何を売るか」を見極め
本物の商品作りと営業プロセス設計に取り組む』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスモデルの再構築において、特に大事なのは商流と物流を重点的に見直すこ
とであり、そこから「誰に何を売るのか」を決めることです。そのためには、「商
品」について再考する必要があります。このセッションでは、商品作りと営業プロ
セス設計を考慮し、具体的にマーケットからどうやって収益を上げるかを解説しま
す。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆Q&Aセッション 16:15〜17:00
当日会場からの疑問・質問に講師がお答えします。
司会:日経ソリューションビジネス編集長・中村建助
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎残席僅か!お早めにお申し込みください!◎
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ http://coin.nikkeibp.co.jp/coin/wat/semi/0809/
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(講演タイトル・内容・時間は変更になることがあります)